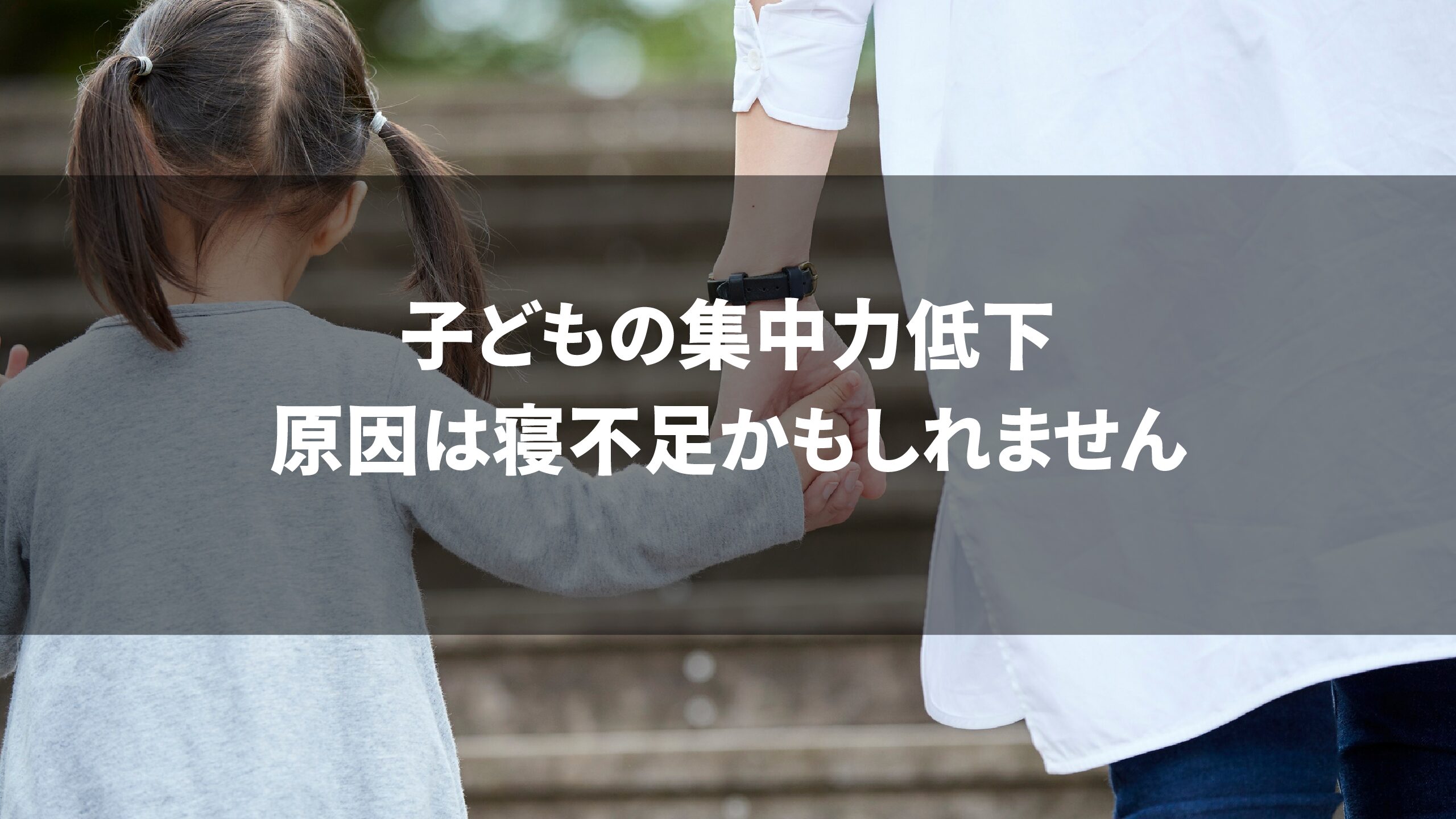「うちの子、授業中にぼーっとしている」「姿勢がだんだん崩れていく」と感じたことはありませんか? 実は、その背景には「睡眠不足」が隠れていることがあります。日本の小中学生の平均睡眠時間は、文部科学省の調査によると推奨よりも約1時間短いという結果も出ています。 睡眠不足は単に眠そうに見えるだけでなく、姿勢や集中力に直結する深刻な問題を引き起こします。

睡眠不足が引き起こす姿勢と集中力への影響
筋緊張の乱れで姿勢が崩れる
睡眠中は、日中に酷使した筋肉や神経系が回復します。睡眠が足りないと、この回復が不十分になり、体幹や首・肩まわりの筋肉が緊張しやすくなります。 その結果、椅子に座っていても背中が丸くなったり、頭が前に出たりといった「疲れ姿勢」が現れやすくなります。理学療法の現場でも、慢性的な寝不足の子どもは、姿勢保持時間が短い傾向があります。
脳の働きが低下し、集中が続かない
脳は睡眠中に記憶を整理し、情報処理能力を回復させます。特に深いノンレム睡眠は、前頭前野(集中力や判断力を司る部分)の機能を回復させる重要な時間です。 睡眠不足になると、この回復が不十分になり、授業中に注意が散漫になったり、ちょっとした刺激で気が逸れたりします。 米国の研究では、睡眠時間が7時間未満の小学生は、8〜9時間寝ている子に比べ、学習課題の正答率が10%以上低下するというデータもあります。
疲れやすく、運動嫌いになる悪循環
十分な睡眠を取らないと、日中の活動エネルギーが不足し、「体を動かすのが面倒」という状態になりがちです。運動不足はさらに姿勢保持筋を弱らせ、集中力の低下にも拍車をかけます。 結果として「運動しない → 姿勢が悪くなる → 集中できない」という悪循環に陥ることも少なくありません。

家庭でできる睡眠改善の工夫
寝る前のルーティンを作る
毎日同じ時間に就寝できるよう、寝る前の行動をパターン化しましょう。 例えば、「入浴 → 水分補給 → 本を読む → 消灯」というように決めると、体が「これから眠る時間だ」と自然に認識しやすくなります。 私の家では、夜9時以降はテレビやゲームをやめ、照明を暗めにするだけでも寝つきが早くなりました。
光・音・温度の調整
- 光:寝室の照明は暖色系にし、就寝1時間前から明るさを落とす
- 音:静かな環境を作り、必要ならホワイトノイズを使う
- 温度:夏は26〜28℃、冬は18〜20℃を目安にする
特にブルーライトは睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑えるため、就寝前のスマホやタブレット使用は避けましょう。

朝の光を浴びて体内時計を整える
朝起きたらカーテンを開け、自然光を浴びることで体内時計がリセットされます。これにより夜の眠気が自然に訪れやすくなります。 私が指導した家庭では、朝の散歩を習慣にしただけで、子どもの寝つきが改善し、日中の集中力も高まったケースがあります。
まずは1週間、睡眠を見直してみましょう
もしお子さんが授業中に姿勢が崩れやすい、集中力が続かないと感じたら、睡眠時間と質を見直すことから始めてください。 生活習慣を少し整えるだけで、姿勢も集中力も改善する可能性があります。
行動の第一歩
今夜から「就寝1時間前はブルーライトオフ」を試してみましょう。効果を感じられたら、寝室環境や就寝ルーティンの改善も取り入れてください。 継続することで、お子さんの学習態度や姿勢に変化が現れるはずです。
→ 他の家庭での改善事例や具体的な運動法も知りたい方は、関連記事をご覧ください。